
[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
シェラックをオンラインで小売りしてくれる頼もしいお店を紹介。(次のページの冒頭に追記としてあります。)
 シュラック仕上げ(改訂版)
シュラック仕上げ(改訂版)
このノッティーワークショップでシェラック仕上げを取り上げたところ、ホームページを見た方からたくさんの反響を頂きました。このページを参考にして実際に使用された方からのメールのほとんどがその素晴らしさ(扱いやすい、乾燥が早い、仕上がりがよい、無害、環境に優しい、色合いが良い、コストが安い、etc)について触れていました。
その反面、説明が足りなかった部分も多いことが反響からも感じられました。今回は改訂版として加筆修正してあります。

シュラック仕上げについて詳しく解説しています。
シュラック=シェラック=セラック=Shellac です。英語の発音はセラックではなく、
シュとシェの中間のような発音です。本書ではシュラックと書いたりシェラックと書いたりします。
3000年以上昔に使われていた記録があるほど、歴史のある古い仕上げの手法です。
欧米のウッドワーカーからは魔法の仕上げと呼ばれ、今でもプロ/アマを問わず多くの人が愛用しています。
私も最近数年使ってみて、すっかりこの仕上げが気に入りました。もちろん他の仕上げ方法のようにシェラックにも長所、短所があります。すべての状況に対応できる万能の仕上げではありません。それをよく理解の上で使ってください。あなたもきっとこの仕上げ方法が選択肢の一つに加わり、作品に奥行きが増すことでしょう。
シェラックはフレークの状態では無害です。アルコールに溶いた状態では火気に気をつけるとともに、小さな子供の手に触れないように注意してください。使用の際は換気に気をつけて安全メガネと手袋を着用してください。
シュラックはインド、タイなど南方のアジアに生息するラック虫の殻から作られます。これら
ラック虫は樹木に寄生して樹液を吸います。そして自身の体を包んだり、産卵のために木の枝に殻を作ります。このラック虫から分泌された、樹液をたっぷり含んだ殻がシェラックの原料になります。これを精製してシュラックを作るのですが、精製の度合いによっていくつかに分かれます。
精製度が高くなるにつれ、茶褐色から薄い黄色に変わっていきます。
精製度の低い順から、


以下に手持ちのシェラックフレークの写真を示します。
ボタンラック (Waxed) 本当にボタンのような形をしています。堅いのでフレンチポリッシュに適しています。非常に溶けにくいです。

ガーネット・ラック(左:Waxed , 右:Dewaxed)


オレンジ・シュラック(左:Waxed , 右:Dewaxed)


レモン・シュラック (Dewaxed)

スーパー・ブロンズ・シュラック (Dewaxed)

ウルトラ・ブロンズ・シュラック (Dewaxed)

通常、シェラックは固体です。これをアルコールに溶かして使用します。一方、ホームセンターで売っているセラックニスはシェラックを原料にして作られたものもありますが、詳しい原材料が書かれていないのでわかりません。他の成分が入っていたり、油脂分が残っていたり防腐剤が入っている可能性があります。またラッカーとはシェラックを化学的に合成させて作ったもので、シェラックとは全くの別物です。シェラックが自然物で収穫や品質が一定しないことから考え出されたものです。溶媒もアルコールではなく、有害なラッカーシンナーを使用します。

まず大きな長所が人体に対する影響が少ないということです。食品、医薬品、化粧品にも使用されます。
食品では粒状チョコレートの表面をツルツルにしたり、柑橘類をツヤツヤに見せる保護皮膜材、レモンやチーズに印字する際のインクにも使用されます。
医薬品としては、酸に強くアルカリに弱いことから胃では溶けずに腸で溶ける錠剤に使われます。(腸溶性皮膜材)ニオイをよく遮断するので、錠剤にコートして薬臭さをカバーするのにも使用されます。
化粧品としてはマニキュア、マスカラやヘアースプレーなどにも使用されるそうです。
これらの項目を見ても誰もがいままでシェラックを食べたことがありますよね。(^^)
シンナーなどの有機溶剤を使用しないので、環境にも人体にもやさしいです。とくに欧米ではHAPS(大気汚染物質)やVOC(有機揮発物質)についての規制が厳しいです。
油性、水性、どちらの仕上げとも相性がいいです。一部の文献では相性が悪いと書いていますが、ブロンズ以上の精製度で、dewaxedを使用すれば問題ないです。
渋い艶消しから鏡面のようなピカピカ仕上げまで、方法によって使い分けられます。
ホルノアルデヒドもよく遮断します。(これは手作り家具には関係ないですけど。)
引き出しの外側などにオイルや油性ウレタン仕上げをすると温度、湿度によって引き出しが固着してしまうことがありますが、シェラックですとこれもありません。
シェラックの特徴の一つに乾燥が早いというのがあります。ウレタンやオイル仕上げのように乾燥するまで丸1日待つ必要はありません。DewaxedのほうがWaxedよりも乾燥が早いです。通常は1時間もあれば十分乾燥します。春先の陽気のいいときで、Dewaxedを使用すれば15分程度で乾燥します。塗った直後でもアルコールが蒸発してしまえば、ニオイは全く残りません。すぐに室内で使用できます。オイルや油性ウレタンのようにイヤなニオイが残るということもありません。
週末に作品を作る場合に、日曜日の昼過ぎに作品が出来上がったとします。前日に溶いておいたシェラックを使用すれば、3時間もあれば4回塗りができるので、その日の夕方には仕上げも完了します。出来上がった作品をすぐ家の中に入れて家族から「くさ~い」と文句が出ることもないです。その晩の家族だんらんの際、作品を前にしてお父さんはヒーローになれます!! (^^)
シュラックはアルコールを溶媒にするのは前述の通りです。これは可逆性の反応です。
したがって溶媒に出会うとまた溶けます。したがってアルコールには弱いです。
ただしこの短所が時には長所になります。失敗してももう一度アルコールで拭いてやり直す
ことが可能です。ムラになったり、液だれしたまま乾燥してしまったときでもやり直しがができます。
以上の理由からテーブルの天板には向きません。(特に我が家のテーブル)(^^; ただテーブルの天板でもトップコートではなく下地には使用できます。
水分にも弱いと書かれている文献もありますが、それはシュラックの種類と溶媒の種類によります。ブロンズ以上の精製度のDewaxedと純度の高いアルコールの組み合わせは水にも強いです。
脱脂したシェラックでは油性、水性、どちらの仕上げとも相性がいいです。
乾燥があまりにも早いのでそれがかえってムラになったりします。その場合は気温の低いときに
作業をしたり、溶媒を多めにして薄くしたり、リターダー(おそらく中身はブチルアルコール)と呼ばれる乾燥のやや遅い溶媒が発売されているので、これを利用したりします。
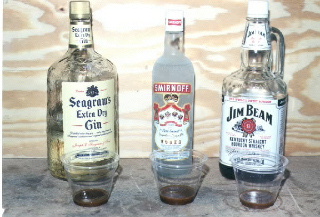
下の写真は薬局で手に入れた2種類の消毒用アルコールでウルトラブロンズシェラックを溶かしたものです。(24時間後)左側の写真がアルコール濃度70%、右側が99%と書いてあったものです。いずれもイソプロピル・アルコールです。濃度70%のほうはまだ溶けきってなく、フレークの周りに白いブヨブヨができています。一方濃度99%のほうは完全に溶けています。


またアルコール中の水分は木目をケバ立たせます。(スポンジング)この点からもなるべく濃度の高いアルコールを使用することをお勧めします。もし複数種類のアルコールが入手できて、どれを使うか迷ったら、このスポンジングを利用して、濃度を確かめられます。まず木片を600番ぐらいまでの紙ヤスリで丁寧にツルツルに磨きます。つぎにアルコールのみをこの木片に塗ります。乾いたあとで、木肌をチェックしてみて、最もスポンジングが少なかったのアルコールが溶媒に最適ということになります。
私は安いのでメタノールを5%程度含んだ変性アルコールを使用していますが、多少水分が入っているらしく、濃度99%のアルコールよりはケバ立ちます。このケバ立ちは初回に塗った時のみで、乾燥後に軽くサンディングしてやれば表面はツルツルになります。
アルコールの種類によってシェラックの膜に特徴が現れますといわれます。メタノールを使用すると膜は硬くなりますが、硬さゆえに表面に小さなヒビが入り、耐水製がやや劣ります。イソプロピル・アルコールを使うと膜は柔軟性を帯び、耐水製が上がると言われています。ただこの点については試したことはありません。
私はバーテンダーが使用する注ぎ口をアルコールの瓶に装着しています。アルコールは蒸発が早いので、塗っている間も時々濃度調節が必要です。そんなときは片手でチョイチョイとアルコールを注いでやります。その他にもお酢のビンや洗剤の容器なども使用しています。

溶媒としてはなるべく純度の高いアルコールを使用し、ハケや容器のクリーニングには純度の低い安いアルコールを使用するというのが賢い選択のようです。

